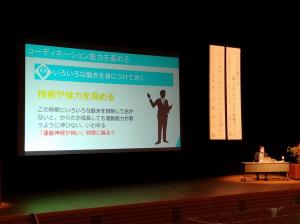本文
教育委員会活動レポート(令和7年2月)
ギャラリートーク「宴(うたげ)ー作花(さっか)家のおもてなしの記録」歴史民俗資料館
|
|
2月22 日(土曜日)11時から第2回目のギャラリートークを開催しました。 1月26日(土曜日)に開催した1回目のギャラリートークと同じように、前半を古文書、後半に器類の話題を提供しました。 |
プログラミングと積み木 放課後子ども教室
|
|
2月19日(水曜日)、放課後子ども教室「出合いちょうっこ」の今年度最後の活動がありました。放課後子ども教室は、放課後や休日に子どもたちが地域の方々とスポーツ・文化芸術活動など様々な体験をし、様々な世代の人と接することで、子どもの社会性や自主性を育むことを目的としています。 この日はプログラミング体験と、おもちゃ遊びをしました。 プログラミングと積み木。一見、デジタルとアナログの代表のようですが、この二つには共通点があります。どちらも、見通しを立てて実行して、できたかどうかを考えます。こうした思考をデジタルでするか、積み木でするかの違いなのです。こうした遊びの中で、いろいろなものを使って、脳みそが汗をかくぐらい考えてほしいと思います。 |
黒電話を使えますか?歴史民俗資料館出前授業
   |
2月6日(木曜日)厚狭小学校、7日(金曜日)本山小学校、13日(木曜日)厚陽小学校の3校で歴史民俗資料館からの出前授業がありました。 3年生では社会科で「昔の暮らしと道具」という学習を行います。授業では、現在の生活では欠かすことができない電気・ガス・水道がない時代の道具について見たり調べたりしながら、昔の人たちが様々な工夫をして暮らしていたことを学びます。社会科の教科書や副読本の「はっけん!山陽小野田」に掲載されている写真等や、出前授業でもってきていただいた歴史民俗資料館に保存されている昔の道具や写真について教えてもらいました。道具を見ては「おじいちゃん、おばあちゃんの家にある」、「トトロで見た」などの声があがっていました。最後は子どもたちが実際に道具を触ってみる体験をしました。箱膳、ダイヤル式黒電話、炭火アイロン等をもったり、使ったりしてみました。黒電話ではうまくダイヤルできず四苦八苦する様子もみられました。授業を通じて、「今の道具って便利だな」「昔の人は道具を工夫して作っていたのがわかった」などの感想を最後に発表しました。 歴史民俗資料館では、昔の道具などの民俗資料を常設するとともに、市内の全小学校での出前授業を実施しています。 |
お金の話 金融教育
|
|
2月10日月曜日、高千帆中学校で、3年生を対象に三菱UFJアセットマネジメントから4名の講師をお迎えして、金融教育を実施しました。金融リテラシー(お金の知識や判断力など)を育成するため、基本的な知識について講義をうけたあと、「ナビナビ資産運用デザインゲーム」をしました。ゲームでは、3〜5人のグループで話合いながら進めていきます。あちらこちらから歓声があがるなか、ゲーム上で約40年の人生を歩みました。最終的に、資産運用についてB〜Sの評価をつけてもらい、講師の方に解説をしていただきました。 中学3年生も卒業すると、3年後には「成人」となります。こうした体験が今後に生きてくれることを期待しています。 |
生徒指導担当者会議及びいじめ問題対策協議会
 |
2月6日(木曜日)、生徒指導担当者会議及びいじめ問題対策協議会を開催しました。各学校の生徒指導担当者に加え、市民活動推進課女性相談支援員、家庭児童相談室相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、青少年健全育成指導員、少年安全サポーター、心の支援室支援員が参加した研修会となりました。 それぞれの立場からの意見交換を行い、課題である「不登校児童生徒について」ついて協議を行ったあと、「いじめ予防授業」についてのワークショップも行いました。 子供たち一人ひとりの元気と笑顔があふれる学校にするために、教育委員会では、学校と連携しながら支援してまいります。 |
生成AIを活用した授業
|
|
2月5日(水曜日)竜王中学校で、生成AIを活用した授業が公開されました。 生成AIを授業で活用する研究は、全国で取り組まれています。本市では、東京学芸大学の鈴木准教授の指導を仰ぎながら研究を進めてきました。 当日、公開されたのは中学校2年生の体育・卓球の授業です。授業では、生徒たちがミニゲームを通して、どのようにしたら勝てるのか、そのためにどんな練習をしたらよいのかを、撮影した自分の写真をもとに、生成AIと対話しながら考えを深めていきます。何度も対話をするうちに、戦術や技術が身についてきます。 このように生成AIをパートナーとして課題解決を繰り返す学びが学習の中心となります。これからは、知識を伝授するというよりも、思考しながら知識を深めていくという授業となっていきます。 この日の様子はNHK山口でも放映されました。 |
地域力・学校力・家庭力向上プロジェクト!
|
|
2月3日(月曜日)に令和6年度第2回「地域力・学校力・家庭力向上プロジェクト!」研修会を実施しました。 協議では、「今年度できなかったことがあるから、来年度は協力して挑戦したい」、「発達段階的に、この学年にはこの活動を仕組んだらどうだろう」といった意見が聞かれるなど、どの校区も熱心に話し合いを行っていただきました。今年度から、新たに地域連携に携わるようになった方には、校区内における地域連携担当者同士の人間関係づくりにもつながりました。 |
市PTA連合会父親母親研修大会
|
|
2月2日(日曜日)不二輸送機ホールにて、令和6年度山陽小野田市PTA連合会父親母親研修大会が開かれました。この研修会は、市内のPTAの実践活動や子育てに関わる講演を参考にして、自校のPTA活動に役立てていこうとするものです。 本年度は、埴生小中一貫校が「できるときに、できる人が、できるほど」をスローガンに進めてきたPTA活動を「保護者の負担軽減」「新しいことにチャレンジ」「地域との連携」という視点から発表されました。 続いて、山口県歯科衛生士の今田千恵美様から「子どもの健口が脳と体に与える影響!?」を、いきいきLABO整骨院の壱岐淳平様から「ゴールデンエイジについて学ぼう」をテーマとしたご講演を拝聴いたしました。 これからの時代も大きく変化し予測困難と言われています。そうした未来を生き抜く子供たちを育てていくためには、今を生きる私たち大人も力を合わせ、学んでいく必要があります。教育委員会としましても、そうしたPTAの活動をより一層支援してまいります。 |