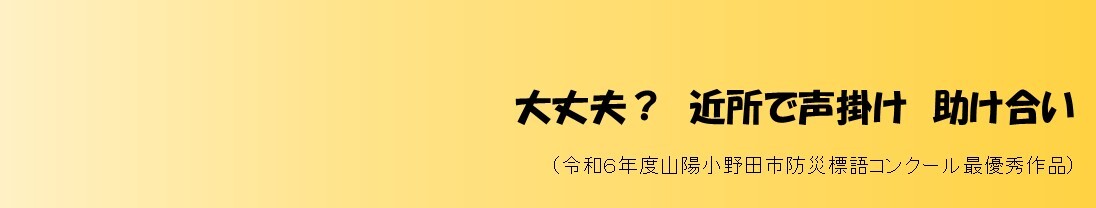本文
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
概要
要配慮者利用施設とは、高齢者、障がい者、乳幼児等の、防災施策において特に配慮を要する方が利用する施設です。要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。これにより、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。また、津波防災地域づくり法に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者にも、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられています。
水防法・土砂災害防止法の改正について(平成29年6月国土交通省作成) [PDFファイル/417KB]
浸水想定区域(洪水・高潮)、災害警戒区域内(土砂・津波)の要配慮者利用施設の所有者または管理者に義務付けられている事項
○ 避難確保計画の作成
○ 避難確保計画作成の市町村長への報告
○ 避難確保計画に基づく避難訓練の実施
○ 避難訓練実施結果の市町村長への報告
避難確保計画
避難確保計画とは、洪水、高潮、土砂災害、津波災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な、次の事項等を定めた計画です。
・防災体制に関する事項
・利用者の避難の誘導に関する事項
・避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
・防災教育及び訓練の実施に関する事項
・自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
・利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
作成の対象となる施設
以下に該当する要配慮者利用施設が計画作成の対象施設となります。
●有帆川又は厚狭川洪水浸水想定区域に位置する施設
【確認方法】
①洪水ハザードマップ(有帆川・厚狭川)を確認する
https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/bosai/kouzui-hazardmap.html
②公開型WEBマップを確認する
https://www.sonicweb-asp.jp/sanyo-onoda/
※ハザードマップの有帆川または厚狭川の浸水想定区域(想定最大規模降雨)にチェックをつけて御確認ください。
●高潮浸水想定区域に位置する施設
①高潮ハザードマップを確認する
https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/bosai/takashio-hazardmap.html
②公開型WEBマップを確認する
https://www.sonicweb-asp.jp/sanyo-onoda/
※ハザードマップの高潮浸水想定区域(浸水深)にチェックをつけて御確認ください。
●土砂災害警戒区域に位置する施設
①土砂災害ハザードマップを確認する
https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/bosai/dosha-hazardmap.html
②公開型WEBマップを確認する
https://www.sonicweb-asp.jp/sanyo-onoda/
※土砂災害ハザードマップ(土石流警戒区域、土石流特別警戒区域、急傾斜崩壊警戒区域、急傾斜崩壊特別警戒区域、地すべり警戒区域)に全てチェックをつけて御確認ください。
●津波災害警戒区域に位置する施設
①津波ハザードマップを確認する
https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/site/bosai/tsunami-hazardmap.html
②公開型WEBマップを確認する
https://www.sonicweb-asp.jp/sanyo-onoda/
※津波ハザードマップ(南海トラフ地震津波想定区域、周防灘断層地震津波想定区域)に全てチェックをつけて御確認ください。
避難確保計画等の作成・提出要領
水防法、土砂災害防止法、津波防災地域づくりに関する法律の規定により、要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成し市役所へ報告する必要があります。作成方法は、①新しく避難確保計画を作成し提出するもしくは②消防法に基づく消防計画に必要事項を書き加え避難確保計画の項目を満たすものを作成し提出することとなります。
提出物
電子メールで提出の場合、(1)から(3)まで、すべて1部のみ提出で可。
(1)避難確保計画作成(変更)報告書 2部
ひな形:避難確保計画作成(変更)報告書 [Wordファイル/18KB]
(2)対象となる災害の避難確保計画 2部
受付し確認後に、1部を返却します。
ひな形:【洪水】避難確保計画 [Wordファイル/25KB]
ひな形:【高潮】避難確保計画 [Wordファイル/25KB]
ひな形:【土砂災害】避難確保計画 [Wordファイル/23KB]
ひな形:【津波】避難確保計画 [Wordファイル/25KB] [Wordファイル/25KB]
(3)避難訓練実施報告書 1部
作成していただいた避難確保計画に基づく避難訓練を、原則年1回以上実施し報告書の提出をお願いします。
ひな形:避難訓練実施報告書 [Wordファイル/9KB] [Wordファイル/21KB]
注意点
●必ずしも雛形のとおりに作成する必要はありません。
●“避難確保計画”は災害時の避難に関する計画であれば、名称は自由です。
●厚生労働省令等に基づく非常災害に対する具体的な計画(非常災害対策計画)や、消防計画を定めている施設は、既存の計画に避難確保計画に定められている項目を追加することで、避難確保計画を作成したとみなすことができます。
●避難確保計画は以下のチェックリストを満たすものとなりますので作成の際に参考にされてください。
社会福祉施設用 チェックリスト [Wordファイル/27KB]
●避難訓練には、施設外の避難先に移動する立ち退き訓練以外にも、避難経路を確認する訓練や情報伝達訓練、職員の非常参集訓練や保護者や家族への引き渡し訓練など、様々な訓練があります。すべての訓練を一度に行うのではなく、立ち退き訓練と図上訓練を交互に行うことや、様々な訓練を分けて行うなど、負担の軽減を図りながら、訓練を継続していきましょう。
訓練終了後には、参加者で意見交換や検証を行い、必要に応じて避難確保計画の見直しを行ってください。
提出先・提出方法
〒756-8601
山陽小野田市日の出一丁目1番1号
山陽小野田市役所 2階 20番窓口 総務課 危機管理室
●電子メール(soumu@city.sanyo-onoda.lg.jp)
●郵送
●窓口に持参
避難確保計画作成のための参考
災害時の情報取得方法の一覧
- 山陽小野田市防災気象情報システム【気象情報・河川監視カメラ、河川の水位の情報等が確認できます】
- 山陽小野田市防災メール【避難情報・気象情報・土砂災害警戒情報・その他市からの防災情報が確認できます】
- 山陽小野田市公式LINE 【避難情報・気象情報・土砂災害警戒情報・その他市からの防災情報が確認できます】
- 山陽小野田市防災ラジオ【情報・その他市からの防災情報が確認できます】
- 気象庁ホームページ【気象情報・土砂災害警戒情報等が確認できます】
- 山口県土木防災情報システム【河川の水位情報・雨量情報等が確認できます】